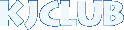мЎ°м„ мңјлЎңл¶Җн„° лӮҙмҠөн•ң лҸҷкөӯкө°мқҖ, лҢҖл§ҲлҸ„В·мқҙнӮӨлҘј лҚ®міҗ, лӮЁмһҗлҠ” лӘ°мӮҙлЎң н•ҳкі , м—¬мһҗлҠ” мҶҗл°”лӢҘм—җ кө¬л©Қмқ„ лҡ«кі лҒҲмқ„ нҶөн•ҙ, лұғм „м—җ мЈҪ лҠҳм–ҙм„ң 묶мқҖ кІғмңјлЎң н•ҳкі мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.л¬ҙм—Үмқ„ мң„н•ҙм„ң мқҙлҹ° мқјмқ„ н–ҲлҠ”к°Җ н•ҳл©ҙ , мӢӨмқҖ к·ёл…Җл“Өмқ„ мӢқлЈҢлЎң н•ҳл Өкі н•ҙ мӮҙлҰ¬кі лҸҷл°ҳмқҙлқјкі мҷ”мҠөлӢҲлӢӨ.лӢӨл§Ң лҸ„л§қм№ҳм§Җ м•ҠкІҢ лҒҲмңјлЎң л°°м—җ л¬¶кі мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.
н•ңкөӯмқёмқҖ мӣҗлһҳ мқјліёмқёкіј к°ҷмқҖ мӢқмғқнҷңлЎң кі кё°лҘј лЁ№м§Җ м•Ҡм•ҳмҠөлӢҲлӢӨл§Ң, л§ҢмЈјм—җ лҚ°лҰ¬кі к°Җм ё л§җкі кё°л“ұмқ„ лЁ№кІҢ лҗҳм–ҙ, н•ңмёө лҚ” мқёмңЎлҸ„ лЁ№кІҢ лҗҳм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.л°•к·јнҳңлҠ” гҖҢн”јн•ҙмһҗмҷҖ к°Җн•ҙмһҗмқҳ кҙҖкі„лҠ”, мІңл…„ ліҖн•ҳм§Җ м•ҠлӢӨгҖҚлқјкі н–ҲмҠөлӢҲлӢӨл§Ң, мҡ°лҰ¬лҸ„ мқјліёмқёмқҙ н•ңкөӯмқём—җ к№”лҙҗмЎҢлӢӨкі н•ҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқ„ мһҠкі лҠ” лҗҳм§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨ.
гҖҢкі л ӨмӮ¬гҖҚмқҳ гҖҢлӘЁнҶ л¬ҙл„Ө 13л…„(1271л…„)гҖҚмқҳ мЎ°м—җ, лӢ№мӢңлҠ” м•„м§Ғ мғҒмҶҚмқёмқҙм—ҲлҚҳ м¶©л ¬мҷ•мқҙ мҝ л№Ңлқјмқҙм—җкІҢ, лӢӨмқҢкіј к°ҷмқҖ мғҒмЈјлҘј н–ҲлӢӨ, лқјкі м“°м—¬м ё мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.гҖҢмң к·ёмқјліёлҜёлӘҪм„ұнҷ” кі л°ңмЎ°мӮ¬кі„мҡ”кө°мҡ© м „н•Ё мһҗкёҲ(мӘҪ)нҺё кұ°мІҳмҲҳлӢ№мқҙм°ЁмӮ¬мң„мӢ л©ҙ진 м •мӢ л ҘмҶҢмЎ°мҷ•мӮ¬гҖҚ
гҖҢлӘҪкі лӮҙмҠө л‘җлЈЁл§ҲлҰ¬к·ёлҰјгҖҚмқ„ лҙҗлҸ„ м•ҢлҸ„лЎқ(л“Ҝмқҙ), н•ҳм№ҙнғҖм—җ мғҒлҘҷн•ң мӣҗкө°м—җлҠ” кё°лі‘мқҙ мһҲм§Җ м•Ҡкі , лҢҖл¶Җ분мқҙ кІҪмһҘ ліҙлі‘мқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.л§җмқ„ л°°м—җ мӢЈкі л°”лӢӨлҘј кұҙл„Ҳ мҳӨлҠ” кІғмқҙ м–ҙл Өмӣ кё° л•Ңл¬ёмһ…лӢҲлӢӨ.к·ёкІғмқ„ л§һм•„ мӢёмҡ°лҠ” мқјліёмқҳ л¬ҙмӮ¬лҠ” мӨ‘мһҘкё°лі‘мһ…лӢҲлӢӨ.
кё°лі‘мқҖ мҠӨн”јл“ңк°Җ мһҲлӢӨмқҳлЎң, лӢЁмӢңк°„м—җ лі‘л Ҙмқ„ 집мӨ‘н•ҳлҠ” кІғмқҙ к°ҖлҠҘн•©лӢҲлӢӨ.лҳҗ, л§җмқ„ нғ„ лҶ’мқҖ мң„м№ҳлЎңл¶Җн„° лӮ®мқҖ кіім—җ мһҲлҠ” ліҙлі‘мңјлЎң н–Ҙн•ҙ м°ҪмқҙлӮҳ м№јмқ„ кұ°м Ҳн•ҙ лӮҙлҰҙ мҲҳ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.мқјліёмқҳ кё°лі‘(м№ҙл§Ҳмҝ лқј л¬ҙмӮ¬)мқҖ, мӣҗкө°мқҳ ліҙлі‘м—җм„ң л¬јлҰ¬м ҒмңјлЎң мҡ°мң„мҳҖмҠөлӢҲлӢӨ.
лӢ№мӢңмқҳ мЎ°м„ мқҖ кі л ӨмҳҖмҠөлӢҲлӢӨ.мҪ”л§Ҳмҷ•мқё м•„мқҙ( нӣ„мқҳ м¶©л ¬мҷ•)лҠ” 1272л…„, мҠӨмҠӨлЎң 진н–үлҗҳкі , мҝ л№ҢлқјмқҙВ·н•ңм—җ мқјліёмқ„ кіөкІ©н•ҙм•ј н•ҳлҠ” кІғмқё кІғмқ„ мқҙн•ҳмҷҖ к°ҷмқҙ, мғҒмЈјн•ҳкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.
мң к·ёмқјліёлҜёлӘҪм„ұнҷ” кі л°ңмЎ°мӮ¬кі„м Ғкө°мҡ© м „н•Ё мһҗкёҲ(мӘҪ)нҺё кұ°мІҳмҲҳ.лӢ№мқҙм°ЁмӮ¬мң„мӢ л©ҙ진 м •мӢ л ҘмҶҢмЎ°мҷ•мӮ¬.
жңқй®®гҒӢгӮүиҘІжқҘгҒ—гҒҹжқұи·Ҝи»ҚгҒҜгҖҒеҜҫйҰ¬гғ»еЈұеІҗгӮ’иҘІгҒ„гҖҒз”·гҒҜзҡҶж®әгҒ—гҒ«гҒ—гҒҰгҖҒеҘігҒҜжүӢгҒ®гҒІгӮүгҒ«з©ҙгӮ’й–ӢгҒ‘гҒҰгҒІгӮӮгӮ’йҖҡгҒ—гҖҒиҲ№гҒ№гӮҠгҒ«ж•°зҸ гҒӨгҒӘгҒҺгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдҪ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒе®ҹгҒҜеҪјеҘігӮүгӮ’йЈҹж–ҷгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒӢгҒ—гҒҰйҖЈгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—йҖғгҒ’гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒІгӮӮгҒ§иҲ№гҒ«зөҗгҒігҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жңқй®®дәәгҒҜгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁж—Ҙжң¬дәәгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘйЈҹз”ҹжҙ»гҒ§иӮүгӮ’йЈҹгҒ№гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжәҖе·һгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгҒҰйҰ¬иӮүгҒӘгҒ©гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«дәәиӮүгӮ’гӮӮйЈҹгҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңҙж§ҝжҒөгҒҜгҖҢиў«е®іиҖ…гҒЁеҠ е®іиҖ…гҒ®й–ўдҝӮгҒҜгҖҒеҚғе№ҙеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгӮӮж—Ҙжң¬дәәгҒҢжңқй®®дәәгҒ«йЈҹгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгӮ’еҝҳгӮҢгҒҰгҒҜгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҺй«ҳйә—еҸІгҖҸгҒ®гҖҢе…ғе®—еҚҒдёүе№ҙпјҲ1271е№ҙпјүгҖҚгҒ®жқЎгҒ«гҖҒеҪ“жҷӮгҒҜгҒҫгҒ дё–з¶ҷгҒҺгҒ гҒЈгҒҹеҝ зғҲзҺӢгҒҢгғ•гғ“гғ©гӮӨгҒ«гҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҠеҘҸгӮ’гҒ—гҒҹгҖҒгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢжғҹеҪјж—Ҙжң¬гҖҖжңӘи’ҷиҒ–еҢ–гҖҖж•…зҷәи©”гҖҖдҪҝз¶ҷиҖҖи»Қе®№гҖҖжҲҰиүҰе…өзі§гҖҖж–№еңЁжүҖй ҲгҖҖе„»д»ҘжӯӨдәӢ委иҮЈгҖҖеӢүе°ҪеҝғеҠӣгҖҖе°ҸеҠ©зҺӢеё«гҖҚ
гҖҢж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒжңӘгҒ гҒ«зҡҮеёқгғ•гғ“гғ©гӮӨгҒ®е®¶жқҘгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«ж”»гӮҒиҫјгӮӮгҒҶгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖӮгҒқгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜиҮӘеҲҶгҒҢе…Ҳй ӯгҒ«з«ӢгҒЈгҒҰж—Ҙжң¬гҒ«ж”»гӮҒиҫјгҒҝгҒҫгҒҷгҖҚгҒЁжҸҗжЎҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжңқй®®зҺӢгҒ®жүҮеӢ•гҒ«д№—гҒЈгҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жңқй®®дәәгӮ„жәҖе·һеңЁдҪҸгҒ®жңқй®®дәәдәҢдё–гҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гӮ’з•ҘеҘӘгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж¬ІжңӣгҒ«й§ҶгӮүгӮҢгҒҰж—Ҙжң¬гҒ«ж”»гӮҒиҫјгӮ“гҒ гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢи’ҷеҸӨиҘІжқҘзөөи©һгҖҚгӮ’иҰӢгҒҰгӮӮеҲҶгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеҚҡеӨҡгҒ«дёҠйҷёгҒ—гҒҹе…ғи»ҚгҒ«гҒҜйЁҺе…өгҒҢгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҢи»ҪиЈ…жӯ©е…өгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮйҰ¬гӮ’иҲ№гҒ«д№—гҒӣгҒҰжө·гӮ’жёЎгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгӮ’иҝҺгҒҲж’ғгҒӨж—Ҙжң¬гҒ®жӯҰеЈ«гҒҜйҮҚиЈ…йЁҺе…өгҒ§гҒҷгҖӮ
йЁҺе…өгҒҜгӮ№гғ”гғјгғүгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзҹӯжҷӮй–“гҒ§е…өеҠӣгӮ’йӣҶдёӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҰ¬гҒ«д№—гҒЈгҒҹй«ҳгҒ„дҪҚзҪ®гҒӢгӮүдҪҺгҒ„жүҖгҒ«гҒ„гӮӢжӯ©е…өгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰж§ҚгӮ„еҲҖгӮ’жҢҜгӮҠдёӢгӮҚгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®йЁҺе…өпјҲйҺҢеҖүжӯҰеЈ«пјүгҒҜгҖҒе…ғи»ҚгҒ®жӯ©е…өгӮҲгӮҠзү©зҗҶзҡ„гҒ«е„ӘдҪҚгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е…ғи»ҚгҒҜеҪ“еҲқгҖҒдёҖж—ҘгҒ§еӨ§е®°еәңгӮ’еҚ й ҳгҒҷгӮӢгҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж„ҸеӨ–гҒ«ж—Ҙжң¬и»ҚгҒҢеј·гҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“жө·еІёгҒ«еј•гҒҚиҝ”гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§дҪңжҲҰдјҡиӯ°гӮ’й–ӢгҒҚгҖҒгҖҢж—Ҙжң¬и»ҚгҒҜж„ҸеӨ–гҒ«жүӢеј·гҒ„гҖҚгҖҢиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ«гҒҜжҸҙи»ҚгҒҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеҗ‘гҒ“гҒҶгҒ«гҒҜгҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгӮ“еј•гҒҚжҸҡгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰеё°гӮӢйҖ”дёӯгҒ§е°‘гҒ—еј·гҒ„йўЁгҒҢеҗ№гҒ„гҒҰиҲ№гҒҢйӣЈз ҙгҒ—гҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮд»ҠгҒ®11жңҲгҒ®гҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒеҸ°йўЁгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
еҪ“жҷӮгҒ®жңқй®®гҒҜй«ҳйә—гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮй«ҳйә—зҺӢгҒ®еӯҗ(еҫҢгҒ®еҝ зғҲзҺӢ)гҒҜ1272е№ҙгҖҒиҮӘгӮүйҖІгӮ“гҒ§гҖҒгғ•гғ“гғ©гӮӨгғ»гғҸгғігҒ«ж—Ҙжң¬гӮ’ж”»гӮҒгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’д»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдёҠеҘҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жғҹеҪјж—Ҙжң¬гҖҖжңӘи’ҷиҒ–еҢ–гҖҖж•…зҷәи©” дҪҝз¶ҷзіҙи»Қе®№гҖҖжҲҰиүҰе…өзі§гҖҖж–№еңЁжүҖй ҲгҖӮе„»д»ҘжӯӨдәӢ委иҮЈгҖҖеӢүе°ҪеҝғеҠӣгҖҖе°ҸеҠ©зҺӢеё«гҖӮ
жғҹпјҲгҒҠгӮӮпјүгӮ“гҒҝгӮӢгҒ«еҪјгҒ®ж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒжңӘгҒ (зҡҮеёқгғ•гғ“гғ©гӮӨгҒ®)иҒ–гҒӘгӮӢж„ҹеҢ–гӮ’и’ҷпјҲгҒ“гҒҶгӮҖпјүгӮүгҒҡгҖӮж•…гҒ«и©”пјҲгҒҝгҒ“гҒЁгҒ®гӮҠпјүгӮ’зҷәгҒ—гҒҰгҖҒи»Қе®№гӮ’ж•ҙгҒҲгҖҒз¶ҷзіҙпјҲгҒ‘гҒ„гҒҰгҒҚгҖҒзі§йЈҹгӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁпјүгҒӣгҒ—гӮҒгӮ“гҒЁгҒӣгҒ°гҖҒжҲҰиүҰе…өзі§гҒҫгҒ•гҒ«й ҲпјҲгҒҝгҒЎпјүгҒ„гӮӢжүҖгҒӮгӮүгӮ“гҖӮгӮӮгҒ—жӯӨдәӢпјҲгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁпјүгӮ’д»ҘгҒҰгҖҒ(зҡҮеёқгҒҢпјүиҮЈпјҲеҝ зғҲзҺӢгҒ®гҒ“гҒЁпјүгҒ«е§”пјҲгӮҶгҒ пјүгҒӯгҒ°гҖҒеҝғеҠӣгӮ’е°ҪгҒ—еӢүпјҲгҒӨгҒЁпјүгӮҒгҖҒзҺӢеё«пјҲзҡҮеёқгҒ®гҒ“гҒЁпјүгӮ’е°ҸеҠ©гҒӣгӮ“гҖӮвҖ•вҖ•гҖҺй«ҳйә—еҸІгҖҸгҒ®гҖҢе…ғе®—еҚҒдёүе№ҙгҖҚгҒ®дёҖйғЁ